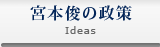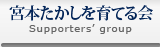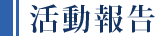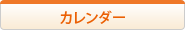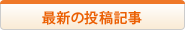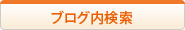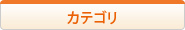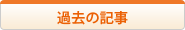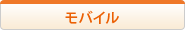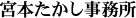3月19日。
視察第2日目、最初の訪問地はむつ市にある日本原子力開発機構の「むつ科学技術館」です。 同施設の中心となる展示物は原子力船「むつ」に関するもので、私もテレビなどでニュースとして聞いたことがある程度の知識だったので、その歴史などについてしっかり理解するいい機会を得ました。
むつとは1969年に建造計画が決まり1968年に着工、1972年に核燃料が装荷され1974年に出力上昇試験が太平洋上で開始された原子力船です。試験開始早々の低出力で放射線漏れが発生し、帰港を余儀なくされましたが地元むつ市の市民は放射線漏れを起こした本船の帰港を拒否し、長崎県佐世保市、むつ市大湊港での母港化反対運動により帰る場所を失ったまま、長い話し合いの末に新母港としてむつ市関根浜港が決まりました。
1990年にむつ市の関根浜港岸壁で低出力運転の試験を行い、その後4度の航海中に出力上昇試験と公試を行なった結果、1991年2月に船舶と原子炉について合格証を得ました。
その後、1992年1月にすべての航海を終了した。現在は、ディーゼル機関に積み替えられた船体が独立行政法人日本海洋研究開発機構(JAMSTEC)の「みらい」として運航されているほか、取り去られた原子炉がむつ市のむつ科学技術館で展示されている。(wikipediaより抜粋)


(写真左:展示されているむつの原子炉 右:中央管制室)
上の写真からも分かるかもしれませんが、中央管制室のメーター類がすべてアナログ。液晶モニターなども見当たらず歴史を感じさせる管理システムでした。
原子力船は巨大かつ長期間運航させてたくさん稼ぎ続けなければ採算が取れないという経済性の観点から日本を含む西側諸国の原子力船計画は全て中止されているということですが、原子力を発電のみならず動力として利用するという観点からは、小型化が可能になれば自動車などに利用できることになり、すごく夢のある話であり、やめてしまうのはもったいないなという素直な印象を持ちました。
我々の次の訪問は「リサイクル燃料貯蔵株式会社」のリサイクル燃料備蓄センターです。同社は東京電力80%、日本原子力発電20%の資本割合にて平成17年11月に設立された会社で、株主となる2社から排出される使用済燃料を再処理されるまでの間、厳密な管理により貯蔵するため、設立されました。
現在は管理棟としての建屋があるのみで、施設の中心となる貯蔵建屋については現在、造成が完了したにとどまっており、2012年7月の事業開始を目指しているそうです。
同社では最終的な貯蔵量は5,000トン(東京電力4000トン/日本原電1,000トン)を考えており、施設の使用期間を50年としている。従って、その施設において50年を経過した時点では貯蔵施設は空となり解体に入る。また、事業開始後40年目までに、貯蔵したリサイクル燃料の搬出について、地元と協議する計画とのこと。つまり、50年の間に万が一、現在の日本原燃などにおける使用済み燃料の再処理計画が頓挫した場合においても50年を超えて貯蔵されることはなく、電力事業者2社の責任において貯蔵物は搬出される。
一回の搬入については8体のキャスク(全長5.4m、直径2.5mの円筒形金属製の使用済燃料収納体)の搬入を計画、1体当たり約10トンの使用済燃料が収納されるので一回で約80トンの搬入となる。これを年4回実施する計画なので、年間約300トン(≒80トン×4回)の搬入となる。




(写真 左上:ミーティング風景 右上:管理棟屋上より敷地内を展望する 左下:貯蔵センター建設予定地 画像右下:貯蔵センターイメージ図/同社ホームページより)
同社の施設は使用済燃料の再処理までの貯蔵施設、いわいる中間貯蔵施設としては日本初の施設となります。 日本の原子力発電所、合計で54基から排出される使用済燃料合計は現在計画中の日本原燃の再処理施設が稼働してもその処理能力(800トン/年)を大きく上回るものであり、同センターのような中間貯蔵施設が今後、全国に複数必要となってくるわけです。
その貯蔵のリスク、およびなし崩し的に当初想定した貯蔵期間が延長されることから判断して発電所そのものよりむしろ危険度は低い施設なのではという印象を持ちました。
さて、一行の次の訪問地は電源開発株式会社(通称:J-パワー)が大間町に建設中の大間原子力発電所建設現場です。この発電所は同社としては初となる原子力発電プラント(水力、火力については実績あり)であり、通常現在の軽水炉におけるプルサーマル発電ではMOX燃料を全体の1/4ほど使用するのに対し、すべてMOX燃料にて発電を行ういわゆるフルMOX発電所となります。
同社の概要と視察報告についてはリポートにまとめたいと思っていますので完成次第、このホームページにアップいたします。