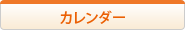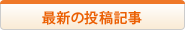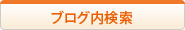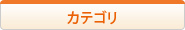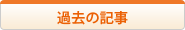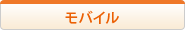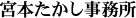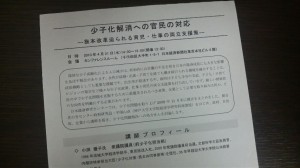 4月21日。
4月21日。
日本経済研究センター主催による「少子化解消への官民の対応 -抜本改革を迫られる育児・仕事の両立支援策ー」というテーマでのセミナーに参加いたしました。
パネルディスカッション形式でのセミナーでパネラーとして、小渕優子衆議院議員(前少子化担当相)、草刈隆郎日本郵船取締役相談役、前田正子元横浜市副市長、宇南山卓神戸大学準教授/日本経済研究センター特別研究員の4名です。それぞれの発言の要旨は以下の通り。。。
宇南山 卓氏
同氏からは少子化に関する調査結果についての話がありました。
○少子化の原因は既婚女性の産む子供の数が減ったからではなく、結婚をする女性が減ったことによる。既婚女性の産む数はこの十年間ほとんど変化していない。
○誰が結婚しなくなったかという点は調査結果から都市部の大卒以上の高学歴の女性という結果が出ている。その半面結婚しない(できない)男性は地方の低学歴層と需要と供給のミスマッチ状況である。
○結婚しない理由は女性の高学歴化と男女の賃金格差の縮小により収入が確保されている現在、結婚して家庭に入ることによりこれらの収入を放棄しない、つまり「結婚の採算性が悪くなった」ことがあげられる。
○これらのことから少子化対策のテーマは結婚が合理的な選択となるようにすること、つまり結婚による女性の離職率を引き下げることにある。結婚への補助金的な政策も考えられるが巨大な財源の確保が必要であり非現実的であろう。この意味で保育所の整備が言い古されてはいるが最も効果のある施策となろう。この指数として通常保育所定員率(保育所の定員/0~6歳の人口)でみることが多いがこれは既に生まれた子に対する充足率であり潜在的需要がどれだけ満たされているかを表さない。従って潜在的保育所定員率(25~34歳女性の人口)で見ていく必要がある。
小渕優子氏
同氏からは少子化担当相時代の経験を踏まえ、国としての政策について話がありました。
○国として少子化対策についてはこの20年間行っているが、大きな成果は上がっていないという自戒の念はある。政策のポイントは結婚支援にあることは理解していたが、結婚は個人と個人の問題であり国として関与すべきものではないという観念が根底にあったと考えられる。
○政府として少子化対策上すべきことは以下の3点に集約されると考える。
<経済的支援>おなかに赤ちゃんができてから出産まではお財布を持たずにすべてに医療が受けられるという方針で政策立案を行った。
<環境整備>子供が病気にかかった時には保育所も受け入れてくれないため、その場合に小児デイケアなどの整備が必要となる。
<意識改革>この部分がもっとも難しいテーマであるが、女性の生き方の幅が大きくなってきているが、この大きさほど男性の意識は変わっていない。少子化対策には男性の理解が不可欠である。
○自分が担当しているときにやるべきテーマというのはかなり明確に理解していたと思っている。しかし、常にぶつかるのは財源の手当ての問題。現政権では子供手当ということで5兆を上回る予算を設定する意向であるが、その何割かで施設整備など十分行えると考えている。この意味で現金支給によるばらまき政策でどの程度、少子化に歯止めがかかるか、また、手当てが純粋に子供のためではなく単に消費されないか危惧している。
草刈隆郎氏
同氏からは企業経営の立場からの女性の労働力の利用について話がありました。
○少子化による労働人口の減少という大きな課題の下、「女性パワー全開実現企業」が勝ち残るという方針で女性の登用などを行ってきた。
○具体的には女性のお茶くみを全面禁止、給茶機を導入した。従来の男子業務の女性へのシフトを奨励、給与体系には中間に「準総合職」を設け、総合職への転換も可能とし評価制度も男性並みとした。現在はIT技術などの発展により船長業務も変化しており、地上からコントロールする部分が大きくなってきており、船長業務も女性が行うケースも見られている。
○育児に関しても支援していく意向で、育児休業も産休満了日より最大2年間認めており女性の取得率は100%となっている。育児のため最大1日2時間の勤務時間の短縮が認められ、短縮された時間は前年度に打ち切られた年次休暇の遡及的費消が可能。子供が小学6年までは年5日の看護休暇を認め、前年度に打ち切られた年次休暇の遡及的費消が可能。
前田正子氏
同氏からは全横浜副市長として教育、医療、福祉を担当したときの経験を踏まえ話がありました。
○在任4年間で116か所の保育所を新規に開設したが、人口の流入を背景に待機児童は一向に減らないという結果であった。
○担当して分かったことだが、自分が就任するまえに描いていた具体的な政策テーマは実は実態である課題の2,3割しかカバーしていなかった。保育所に入りたいと言って申請するなど施策としての育児支援を受けたい人たちは実は社会生活を行っていくうえでのパスポートを持っている人たちである。本当に問題となるのはパスポートを持っていないと表現される児童虐待や生活苦などの問題を抱えた人たちであり、経済的な支援を受けなければ生きていけない人は支援を受けてもお金の生きた使い方も知らず、経済的支援だけでは立ち直れない人がほとんどである。
<所感>
○保育所の整備という伝統的な手法が少子化にもっとも効果があるという認識を新たにした。宇南山氏が提唱する「潜在的保育所定員率」は理にかなった指数であるとともに福井県がこの物差しにおいて全国2位であることは誇らしげに思えた。今後も議員としてこの数字をフォローしてゆきたい。
○企業における女性活用の具体的な手法については理解できたが、残念ながらこれらの導入がどれだけ企業利益にプラスに寄与できたかのお話が全くなかったのは残念。福井県においても女性の管理職登用の訴えなど積極的な施策展開を行っているが、やはり企業として気になるところはそれらが企業にとってメリットとなるかどうか。。。。 よく、女性の活用に積極的な企業は儲かっているという話も聞くが、前提として高収益企業であり余裕があるからそういった制度の導入ができるとの声も聞く。せめて企業イメージ向上の大きなポイントとなったくらいの話は聞きたかった。
○政策担当者、企業の話を聞いて以下に現政権の子供手当という政策が現状にマッチしていないかという認識を新たにした。前田氏の話からしても莫大な財源に基づく現金支給は子育てに本当に役立つのかは疑問であり、国債を大量発行しての政策実施は将来の子供に禍根を残すことにならないかと大きな危惧を持っている。




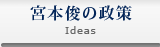

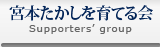

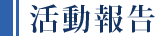


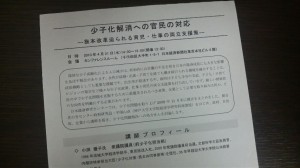 4月21日。
4月21日。