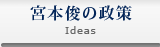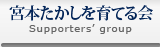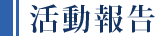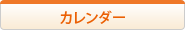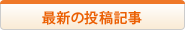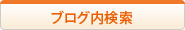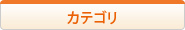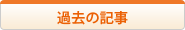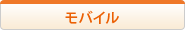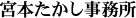[ 活動報告 ]
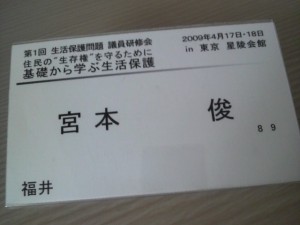
受講名札

福祉事務所での実態に関する寸劇

高木弁護士による説明

慶応義塾大学金子教授の講演
4月17日、18日と「基礎から学ぶ生活保護」というタイトルのセミナーを受講しました。幸いにも今までのところ生活保護を申請して費用を受け取りたいというご要望があり、そのお手伝いをさせて頂く機会はありませんが、現在の不景気による雇用不安が蔓延した状況の中では生活保護は最後の砦となるセーフティーネットだと思われます。そういった意味でやはり議員としてその現状を把握し、どうあるべきかの意見を持つことは必要なことであるとの認識で受講を決めました。
セミナーでは弁護士の方から福祉事務所における実態、「なんとか申請をさせない」職員の態度、法的に申請は何の条件もなくできること(受給適格かどうかは申請の後の話)などの説明がありました。
また、こういった状況を寸劇にして演じられ、わかりやすく実態の把握を行うのに大きな役割となりました。
2日目は慶応義塾大学金子勝教授による「地方議員として社会保障をどう捉えるか」についての講演があり、今までの議論と違う観点からの説明が行われ大きな刺激を受けることになりました。
私もそうでしたが、「働かざる者食うべからず」で代表される日本の価値観からすると生活保護受給者に対するイメージはどうも、怠け者、働きたくない人というイメージが持たれ、このことが制度の普及に大きな障害となっているそうです。しかし、このような社会保障を充実させることは感情的、観念的な弱者救済という点からだけではなく、特に最近は、若年層でも問題になっているわけで、経済政策、つまり、生活保護を受給しても、その後、再生して社会人として労働、納税の義務を果たして頂き、内需拡大の一助を担っていただくという意味でも必要であるとの認識を伺いました。
私がここで感じたのは、企業に対しても不景気で倒産しそうな場合(個人であれば生活に窮し、生きていけないという状態)、セーフティーネット資金の用意がされているわけです。それが個人を対象にすれば生活保護になるわけで、企業支援に比べて議論のテーブルに乗る機会が少なすぎるなというイメージを持ちました。
同教授からの講演の要旨についてはレポートとしてまとめてみましたのでご一読いただけると幸いです。